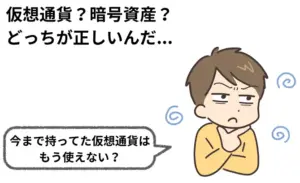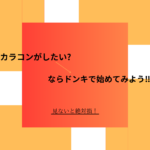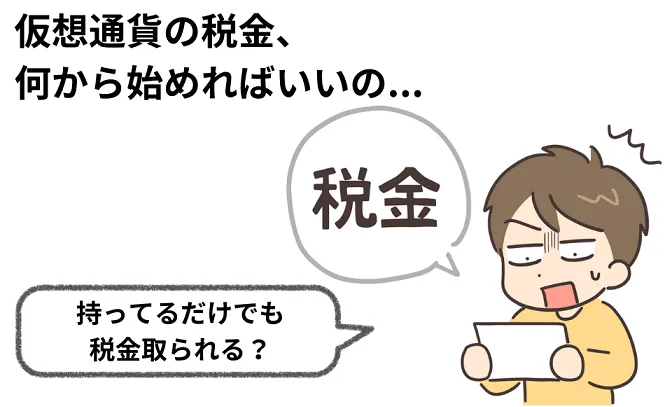
最近、仮想通貨(暗号資産)に投資なさっている方が増えていますね。私も取材を重ねる中で、「ただ持っているだけなのに税金がかかるの?」という質問をよく耳にします。
結論から申し上げると、仮想通貨は「持っているだけ」では原則として税金は発生しません。ただし、売却や交換など、利益が確定したタイミングで課税対象となります。今回は、仮想通貨の税金に関する基本的な考え方から、確定申告の実務まで、分かりやすく解説していきましょう。
この記事のもくじ
仮想通貨に関する税金の基本的な考え方
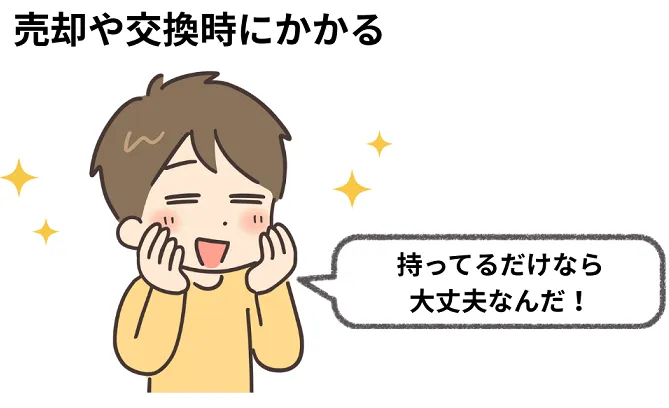
仮想通貨で得た利益は「雑所得」として扱われます。これは、給与所得などと合算して計算される総合課税の対象となります。つまり、収入が多くなればなるほど税率も上がっていく仕組みですね。
ではどんな時に税金が発生するのでしょうか。主なケースは以下の通りです。
・仮想通貨を日本円に換金した時
・ビットコインをイーサリアムなど、別の仮想通貨に交換した時
・仮想通貨で買い物をした時
・マイニングやステーキングで報酬を得た時
これらのケースでは、購入時の価格と売却時(交換時)の価格との差額が利益とみなされ、課税対象になります。
意外と知られていない「保有だけでも」税金がかかるケース
原則として保有しているだけでは税金はかかりませんが、実は例外的に税金が発生するケースがあるんです。
例えば、ステーキングやレンディングといった、仮想通貨を預けて報酬を得る方法があります。この報酬を受け取った時点で、たとえ日本円に換金していなくても課税対象となります。
また、エアードロップと呼ばれる無料配布や、キャンペーンで仮想通貨をもらった場合も要注意です。受け取った時点の価格が所得とみなされる可能性があります。
ハードフォークで新しい通貨が付与された場合も注意が必要です。取得時点では所得は発生しませんが、その後の売却時には、売却額がまるまる課税対象になってしまいます。
確定申告の実務と計算方法
サラリーマンの方でも、仮想通貨の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。また、複数の取引所を使っている場合や副業がある場合は、20万円以下でも申告が必要になることがありますので、ご注意ください。
税金の計算方法は主に2つあります。
1つ目は「移動平均法」。これは仮想通貨を買うたびに平均取得単価を計算する方法です。例えば、10万円で1BTCを買い、その後12万円で1BTCを買った場合、平均取得単価は11万円になります。
2つ目は「総平均法」。これは1年間の購入総額を購入総数量で割って計算します。例えば、1年間で合計100万円使って5BTCを買った場合、平均取得単価は20万円となります。
どちらの方法を選ぶかは、取引の頻度によって変わってきます。取引が少ない場合は移動平均法、多い場合は総平均法がおすすめです。ただし、一度選んだ方法は3年間変更できませんので、慎重に選びましょう。
なお、取引記録は必ず保管しておいてください。特に、取引所の手数料やウォレットの購入費用なども経費として計上できる可能性がありますので、領収書は大切に保管しておくことをお勧めします。
また、海外の取引所を使っている場合でも、日本の税法に従う必要があります。損失が出た場合は他の雑所得と相殺できますが、株式投資などと違って、翌年以降への繰り越しはできません。
税金の計算が複雑になってきたと感じたら、税理士さんに相談するのも一つの手です。確定申告の期限は毎年2月16日から3月15日までですので、余裕を持って準備を始めることをお勧めします。
まとめ:適切な確定申告のために、まずは基本をおさえましょう
仮想通貨は「持っているだけ」では原則として税金がかかりませんが、売却や交換時には課税対象となります。また、ステーキングやレンディングの報酬、エアードロップなど、意外なケースで税金が発生することもありますので注意が必要です。
確定申告については、年間20万円を超える所得がある場合は必須となります。税金の計算方法は「移動平均法」と「総平均法」がありますが、ご自身の取引状況に合わせて選択しましょう。
取引記録の管理は確定申告の基本です。経費として計上できる可能性のある手数料などの記録も忘れずに保管してください。不安な点がある場合は、早めに税理士に相談することをお勧めします。