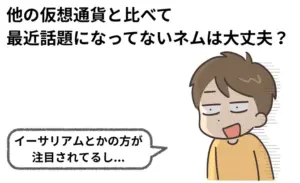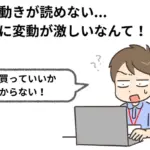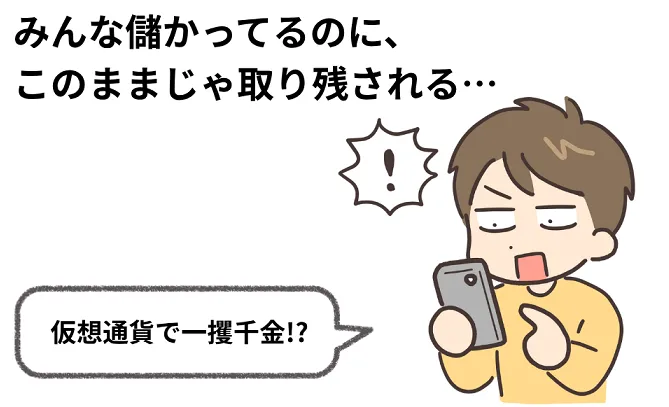
株式投資はもちろん、投資信託やFXなど、様々な資産運用に親しんでこられた方なら、「仮想通貨」という言葉を一度は耳にされたことでしょう。
2017年以降、ビットコインを筆頭とする仮想通貨は、投資市場の新たなプレイヤーとして注目を集めています。驚異的な値上がりで一攫千金を手にした人がいる一方で、暴落で大損を被った人も。今回は、この「仮想通貨バブル」の実態と、これからの可能性についてお話ししていきましょう。
過去2回の仮想通貨バブルから見えてきたもの
まず、印象的だったのが2017年末から2018年初頭にかけてのバブルです。この時期、ビットコインの価格は1年で約20倍にも跳ね上がり、1ビットコインあたり2万ドル(約230万円)近くまで上昇しました。きっかけは、「億り人」という言葉がメディアで取り上げられ始めたことです。「こんな儲かる話があるのか」と、多くの個人投資家が飛びついたわけです。
また、ICO(新規仮想通貨公開)というものが流行し、ベンチャー企業が次々と独自の仮想通貨を発行。ブロックチェーンという技術への期待も相まって、市場全体が熱気に包まれました。ただし、このバブルは長くは続かず、2018年には3,000ドル台まで暴落。多くの投資家が痛手を負うことになりました。
2回目の大きなバブルは、2020年から2021年にかけて起きました。このときは、ビットコインの価格が約6万9,000ドル(約800万円)という史上最高値を記録しています。面白いのは、前回とは様子が違っていたことです。テスラをはじめとする大手企業が投資を表明し、機関投資家も続々と参入。さらに、コロナ禍での世界的な金融緩和で、余剰資金が仮想通貨市場に流れ込みました。
なぜ仮想通貨はバブルを起こしやすいのか
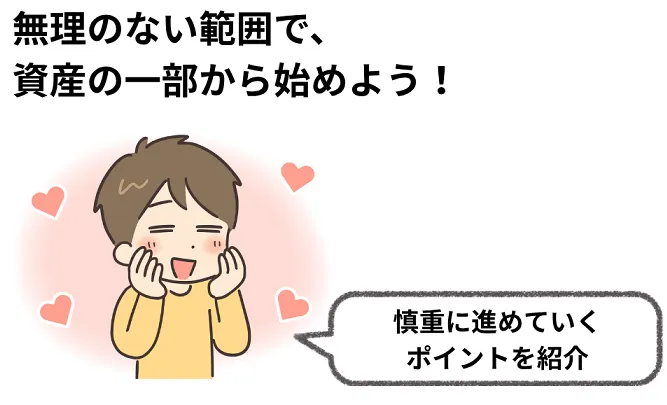
株式市場と比べると、仮想通貨市場にはいくつかの特徴があります。まず、「期待」が先行しやすい点です。「ブロックチェーンは未来の技術だ」「仮想通貨が世界を変える」といった期待が、実用性や価値が確立される前に価格を押し上げてしまうのです。
また、価格の変動が非常に大きいため、短期売買で儲けようとする投機家が集まりやすい環境です。24時間365日取引できることも、投機的な取引を助長する要因となっています。
さらに、まだまだ未成熟な市場であることも見逃せません。規制が不十分で、ハッキングや詐欺のリスクも存在します。FTXの破綻のような大きな事件も起きており、投資家保護の仕組みが十分とは言えない状況です。
今後の仮想通貨市場はどうなるのか
2023年以降、仮想通貨市場は再び活気を取り戻しつつあります。特に注目なのが、米国でのビットコイン現物ETF(上場投資信託)の承認です。これが実現すれば、年金基金や大手金融機関からの資金流入が期待できます。
また、各国で法整備が進められており、市場の透明性や信頼性も徐々に高まってきています。技術面でも、Web3と呼ばれる新しいインターネットの概念や、DeFi(分散型金融)といった革新的なサービスが生まれており、仮想通貨の実用性は着実に広がっています。
ただし、株式投資などと同様、リスクがあることは忘れないでください。仮想通貨は金利やインフレ、国際情勢などの影響を受けやすく、価格の変動も大きいものです。投資をお考えの場合は、十分な知識を身につけた上で、資産の一部に限定して取り組むことをお勧めします。
まとめ:仮想通貨投資は慎重な判断が必要
仮想通貨市場は、2017年と2021年の2度の大きなバブルを経験し、その度に大きな価格変動を見せてきました。当初は個人投資家中心の投機的な市場でしたが、現在では機関投資家の参入や法整備の進展により、徐々に成熟しつつあります。
ETFの承認など、今後さらなる発展が期待される一方で、価格変動の大きさやリスクは依然として存在します。投資を検討される場合は、仮想通貨の特徴や市場動向をしっかりと理解し、ご自身の投資資金の中で無理のない範囲で取り組むことが重要です。新しい技術への期待は大きいものの、あくまでも長期的な視点で冷静に判断することをお勧めします。
【注意】投資は自己責任で行ってください。また、記事内容は作成時点のものです。最新情報は各サービスでご確認ください。